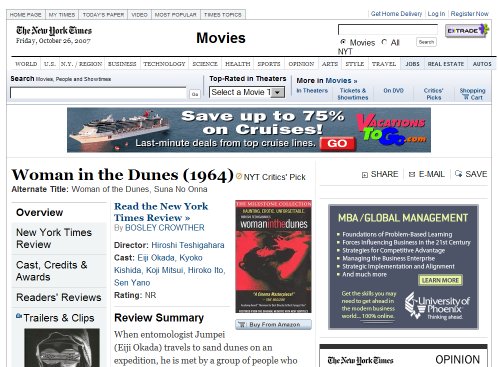「それでも生きる子供たちへ」
ユニセフと国連世界食糧計画が後援した子供をテーマにしたオムニバスで、ルワンダ、セルビア・モンテネグロ、アメリカ、ブラジル、英国、イタリア、中国の七ヶ国の監督が参加している。どれも可哀想な子供の話だが、淡々とした語り口だけに余韻が残る。
メディ・カレフの「タンザ」はルワンダの少年兵の話。大きな銃を脇にジャングルを書きわけて進む少年兵たちの眼光の鋭さにたじろぐ。この小隊ができて二年たつが、最初のメンバーは隊長とタンザしか生き残っていない。少年兵は使い捨てなのだ。
小隊は敵の村に時限爆弾をしかける任務を命じられ、少年兵たちは爆弾のはいったバッグを下げて村に侵入する。タンザも受け持ちの建物に忍びこむが、そこは小学校だった。爆弾をしかけることを忘れて黒板を見つめるタンザ。
エミール・クストリッツァの「ブルー・ジプシー」は得意のロマもの。少年院にはいっているマルヤンは出所が迫っているのに浮かない顔。少年院の中にいれば盗みをしなくてすむが、娑婆に出たらまた盗みをしなくてはならないからだ。
マルヤンを迎えに家族がけたたましいロマの音楽を演奏しながらやってくる。駅の待合室では即興の演奏でみんなを浮かれさせ、その隙に子供たちに金を盗ませる。家族ぐるみ泥棒で暮らしているのだ。
出所したマルヤンは父親から車上荒らしをしてこいと殴られ、早速盗みにいく。ドアを開ける手際が実に手慣れている。しかし、すぐに見つかり、追いかけられる。彼は少年院の塀を乗り越え、また中に。
スパイク・リーの「アメリカのイエスの子ら」はブルックリンのスラムに住むブランカという黒人少女の話。両親はジャンキーだが、娘の前では麻薬は隠そうとしている。しかし、麻薬を射って死んだように横たわっている姿は隠そうとしても隠せるものではない。
ブランカは母親から決まった時間にビタミン剤を飲むようにいわれているが、学校ではしばしば具合が悪くなり、微妙に敬遠されている。彼女は母体内でHIVに感染したエイズ・べービーだったが、そのことを知らされていないのだ。
彼女は体調の悪化と周囲の微妙な視線、両親のひそひそ話から自分がエイズではないかと疑いはじめる。ブランカを演じる少女が愛らしい。
カティア・ルンドの「ビルーとジョアン」はファベーラと呼ばれるブラジルの貧民窟でたくましく自活する兄妹の話。ファベーラでは廃品回収の仲買人がリアカーを貸して貧乏人に廃品を集めさせているが、ビルーとジョアンも大人に混じってリアカーを引いて街に出る。
兄のビルーが思いつきで作ったゲームが街頭で人気を集め、予想以上の収穫があったが、週末なので時間までに仲買人のところにもどらなければせっかくの収穫がふいになる。兄妹は思いリアカーを引いて急ぐが、片方のタイヤがパンクしてしまう。修理してもらってやっと帰りつくが、すでに門は閉じていた。兄妹は必死で開けてくれと叫ぶ。
「ジョナサン」のジョーダン・スコットはリドリー・スコットの一人娘で、父親との共同監督作品。PTSDで戦場カメラマンを廃業したジョナサンが故郷の森の中で経験する幻の戦争の話。ジョナサンは気がつくと子供にもどっていて、見知らぬ少年と少女に導かれて川沿いをさかのぼっていくと、硝煙の立ちこめる戦場に出る。この作品だけ、質が落ちる。
ステファノ・ヴィネルッソの「チロ」はギャングに操られる子供窃盗団の話。
そこで彼らはボスにささやかなお願いをする―。
ジョン・ウーの「